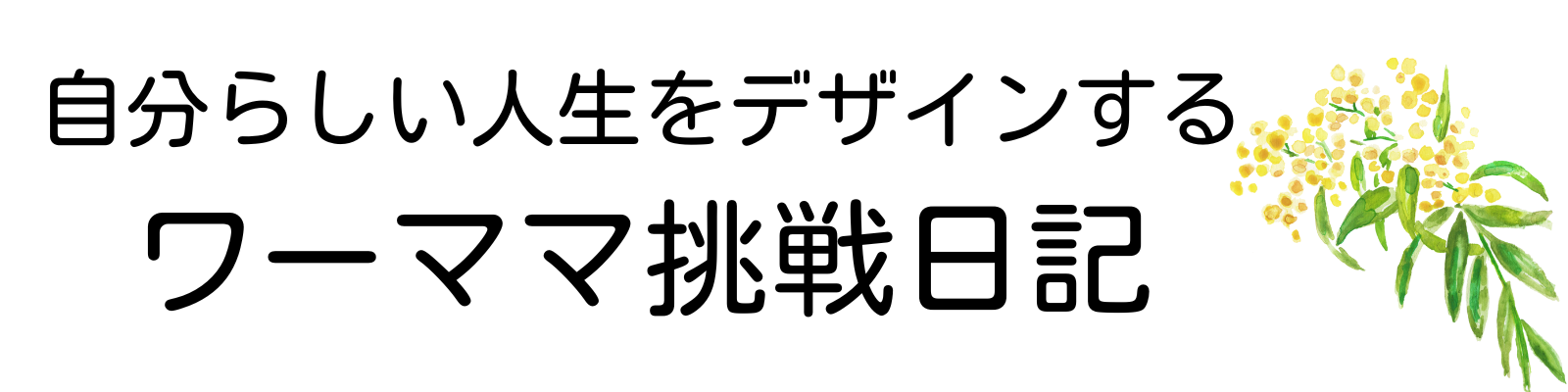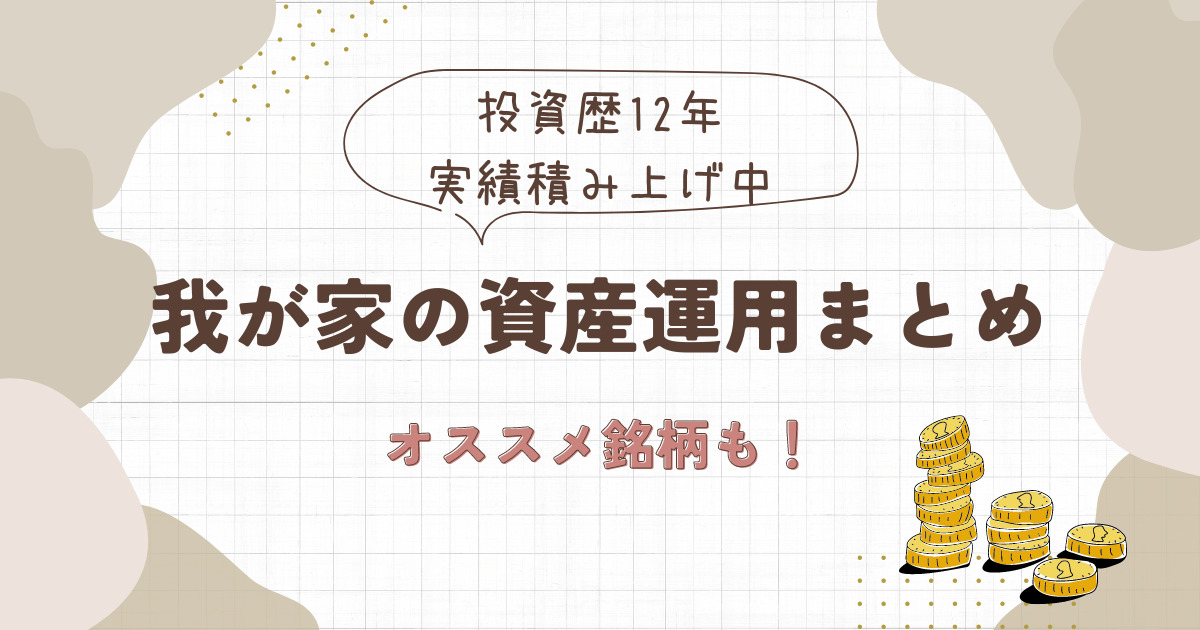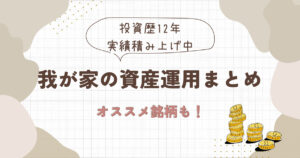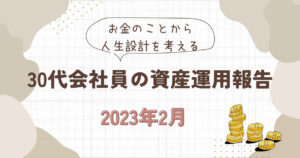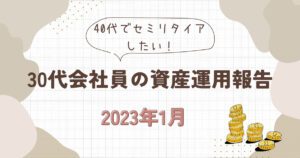最近周りの友人や兄弟などに資産運用方法について聞かれることが増えてきたので、改めて我が家の資産運用について整理してみました。
この記事では、
・「他のご家庭では、どんな資産運用をしているの?」
・「具体的な運用方針について、色々な意見や考え方を知りたい!」
と思っている方が、ご自身の資産運用方針を考える際のひとつの参考事例になればと思って書きました。
(※投資は自己判断です、この記事に書かれている内容に沿って運用されても責任は一切取れません)
方針①節税になる投資の仕組みはすべて活用

まずは基本。政府が国民の資産運用を支援するために用意してくれた制度はすべて使います。結果的にすべて積み立てインデックス投資となっています。
・つみたて NISA 枠は夫婦ともに満額使う
主人と私、それぞれのつみたて NISA 枠は、毎年上限金額いっぱいを、毎月積立しています。
・ジュニアNISAも使いきる
子どもが生まれた2021年からジュニア NISA 制度が終わる2023年度までの3年間、満額を積み立てます。
ジュニア NISA 終了後は、代わりとなる新つみたてNISA の上限金額が大幅に増加するので、今後はそちらを毎月満額積み立てたいです。(満額捻出できるか…まだちゃんとシミュレーションしてません)
子供の大学進学のタイミングで現金が手元になかった場合、これを切り崩してに当てていくことになるのかなあと考えていますが、子どものためにもできる限り長期保有して増やしたいと思っています。
更に第二子が産まれるのは2023年。産後なるべく早く証券口座を開設し、今年の枠80万円分も積み立てたいと思います。
・確定拠出年金・idecoもフル活用
私は会社で確定拠出年金、主人はiDeCoをフル活用しています。大した金額にはなりませんが、やらないよりやった方がマシ。実際に私の確定拠出年金は年率7%で約15年運用しているためかなりの利益額が出ています。
(30年後など長期的に見ると大幅に利益が出る可能性もあり)
・番外編)ふるさと納税も夫婦満額使う
活用できる節約術として、ふるさと納税も見逃せません。
何年も続けているのでだいたい美味しくて使い勝手のよいものも分かってきたので、有効活用して食生活を豊かにしてもらっています(手間の面でも助けられることも多々)。
方針②余剰資金はなるべく投資に回す

できるだけ若いうちに投資元本を増やすことで複利の効果を狙い、利益を増やします。こちらも、積み立てインデックス投資でドルコスト法(定期的に継続買付をすることで購入単価をコントロールする方法)を採用しています。
・夫婦それぞれ、投資比率を高める
先日の資産運用に関する記事でも少し取り上げましたが、私は、資産ポートフォリオの投資部分を(100-年齢)という割合にするべく、急ピッチで積立を行っています。
我が家は基本、夫婦別財布。四半期に1回、各自の資産を洗い出してエクセルで共有し、世帯計の資産推移を管理しています。
まだまだ試行錯誤中&ざっくり管理なので、世帯計の資産ポートフォリオを作成しておらず、世帯としての戦略を練る段階に至っていません。なので、投資比率は各自の判断に委ねているところです。
私は若いうちに投資配分を増やすことでお金に働いてもらって少しでもお金を増やしたい派。
主人は家を買う頭金のことも考えて割と堅実に現金多めのポートフォリオ。ですが、ジュニアNISAは主人が積み立てており、ゆっくりながら着々と投資比率は高めています。
・子どもの貯蓄はすべて投資に回す
出産祝いやお年玉などでもらった現金は、すべて貯金ではなく投資に回すことで、将来子供に渡す貯金額を増やすことを目指しています。(その時に目減りしていたら親が補填することになりますがw)
これは、子どもへの「お金の教育」にもなるかなと考えて始めることにしました。
参考にしたのは個人投資家として有名な虫取り小僧さんの、子どもへのお金の教育方針「子どもの貯金は半分投資・半分貯金で、投資を体感させる」という考え方です。
我が家の場合は、元本と評価額を見せることで投資の意味は伝えられる、という考えから全額投資に回しています。
方針③投資先は米国株(S&P500連動)一択

実際に積み立てている銘柄は、ほとんどがemaxis slim 米国株式(s&p500)というインデックスです。※最近、VOO(バンガードS&P500ETF)の積み立てもはじめました。
(詳しくはコチラの記事で)
【S&P500とは】
米国企業を幅広く代表する約500の企業が採用されている米国市場を代表する株価指数。かの有名な世界的投資家ウォーレンバフェットが妻に自分の死後資産の95%を投資する先として指示した銘柄として有名です。
 kasumi
kasumi資本主義といえばアメリカ。ということで、安定性が高く株価の上昇が期待できる銘柄と理解して採用しています。
そして、emaxis slim 米国株式(s&p500)は、三菱UFJ国際投信の商品で、「手数料を恒久的に他のファンドと比べて最安値にする」と宣言している超人気インデックスファンドです。更に日本政府がつみたてNISAの指定銘柄としても選んでいる安心の銘柄。実際に購入する人も金額も増えており、総資産がかなり高いため売買する際の安心感もあります。
一般的に、あまり投資に時間と労力を掛けずに着実に資産形成したい方は、世界株式のインデックスファンドに投資することがセオリーのようです。世界株式は、アメリカや日本はもちろんインドや中国、東南アジアなど、先進国から発展途上国まで幅広い国に分散投資できます。よって、資本主義が続くかぎり、一国にゆだねてしまうよりもずっとリスク分散されるという面で、安心かつ着実な資産形成が見込めます。(米国が破綻する、なんてことも、なきにしもあらず)
ただし、そんな中でも我が家が米国株を選んだのは、下記のように考えているからです。
アメリカはこれまでリーマンショックやコロナなどの様々な株価暴落を経験しても、どの国より早く株価が回復し、どの国より株価を上昇させてきた実績がある。まさに資本主義として最強の国だから。(国民性も国家も資本至上主義で動いており、かつ人口が増加傾向にある数少ない先進国。)
今後も着実に、かつ全世界株式よりも効率よく、株価を上昇させてくれると期待しています。 ※あくまで我が家の場合。
実際に、現時点での投資成績は非常に良いです。日本株が塩漬けなのに対して、このインデックスのおかげで資産が着実に増えています。
ただし、少し利回りは下がりますが、リスク分散の意味でも全世界株式一択、が模範解答だと思います。



来年からの新NISAについては、満額、全世界株式のインデックスファンドにしようかとも考えております。
方針④証券口座は使いやすさとお得で選ぶ


最後に使っている証券口座を紹介します。
私…楽天証券・SBI証券・auカブドットコム証券
主人…マネックス証券
こども…楽天証券 ※太字が現在積み立てに使っている証券会社
まずは手数料が安くてPCからやモバイルで全ての手続きが完結するオンライン証券が基本です。
更に投資でポイントが貯まるなどの二次的なメリットが得られる証券を選びます。
我が家の場合は、楽天ポイントが貯まる楽天証券をメイン使いにしています。最近始めた米国ETFについては積み立てできるのがSBI証券のみだったので、SBI証券も使いはじめました。
マネックスやカブドットコム証券は過去から使い続けているので使っています。特に不満はありませんが、カブドットコム証券は若干スマホアプリが使いにくいかなと思います。
楽天証券はスマホでも見やすいのでオススメです!
SBI証券やETFについても、しばらく運用しながら色々見えてきたタイミングで記事にしたいと思います。
まとめ


我が家の資産運用方針についてまとめます。
ということで、友人や兄弟に伝えている内容を簡単にまとめます。
・楽天証券ですぐにつみたてNISA(子どもがいればジュニアNISA)フル活用(2023年〜新NISAも早期フル活用目指す)
・銘柄は全世界株式or米国株式あたりで自分の価値観に合わせて検討
(ファンドは手数料これからもずっと最安値を宣言中のemaxis slimがオススメ!)
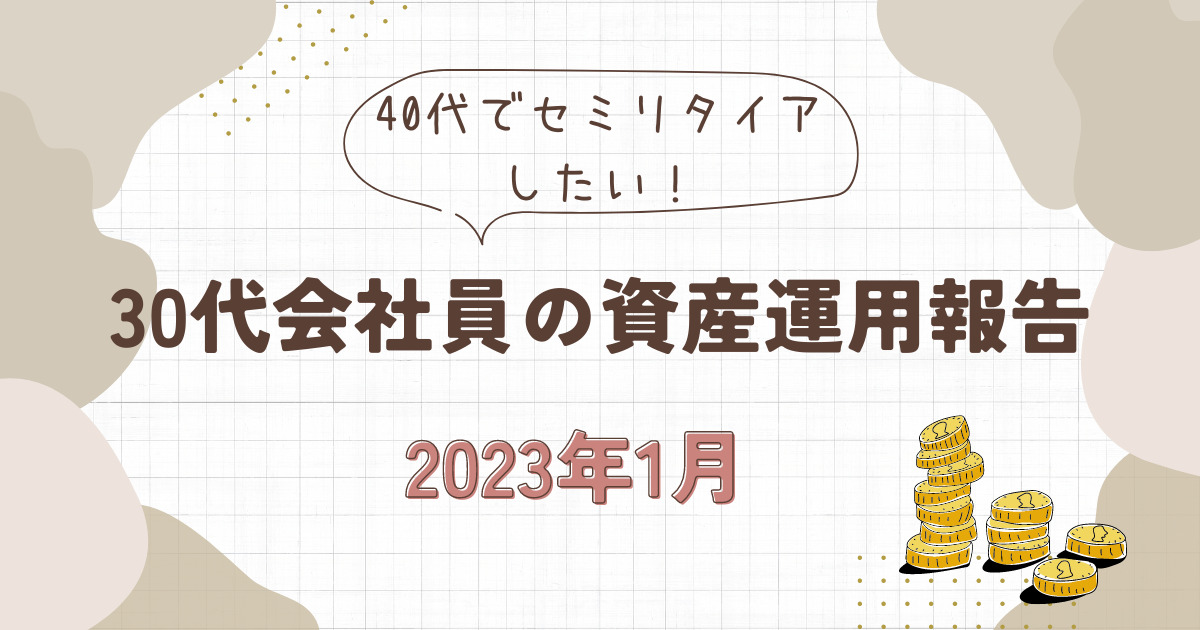
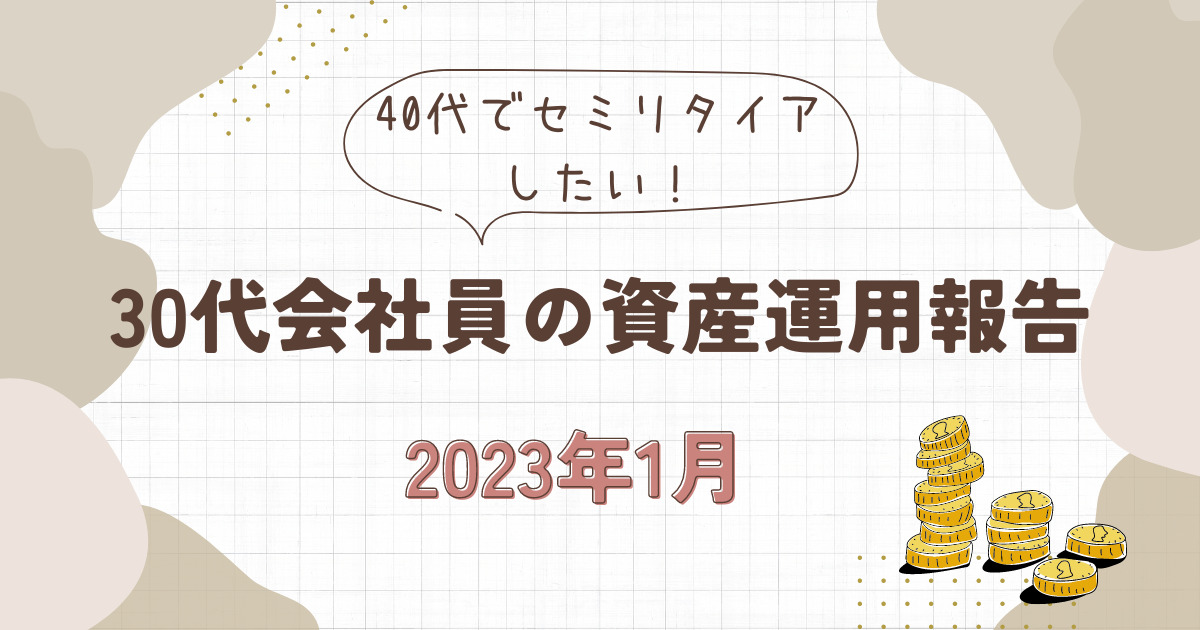
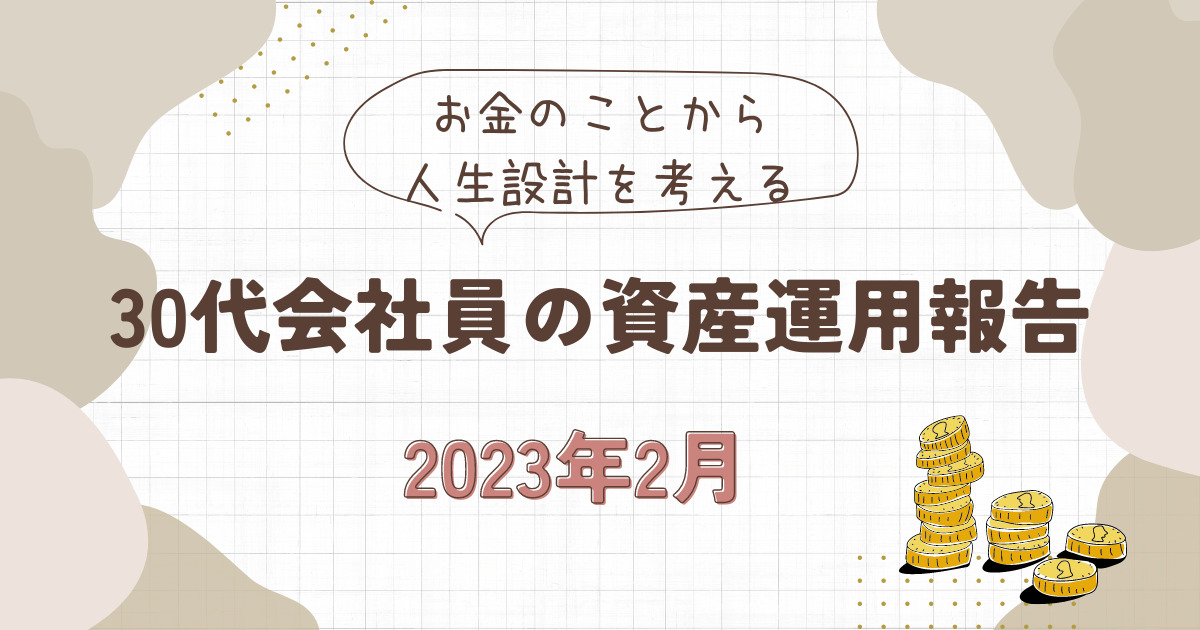
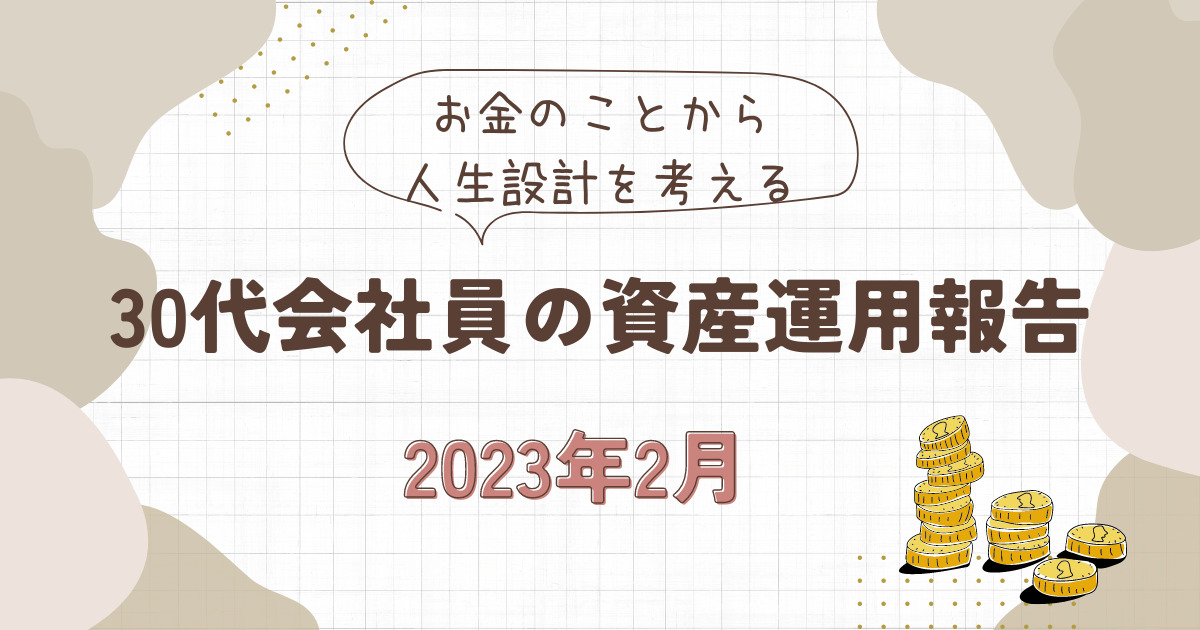



2023年からの新NISAもうまく活用していきたいね!