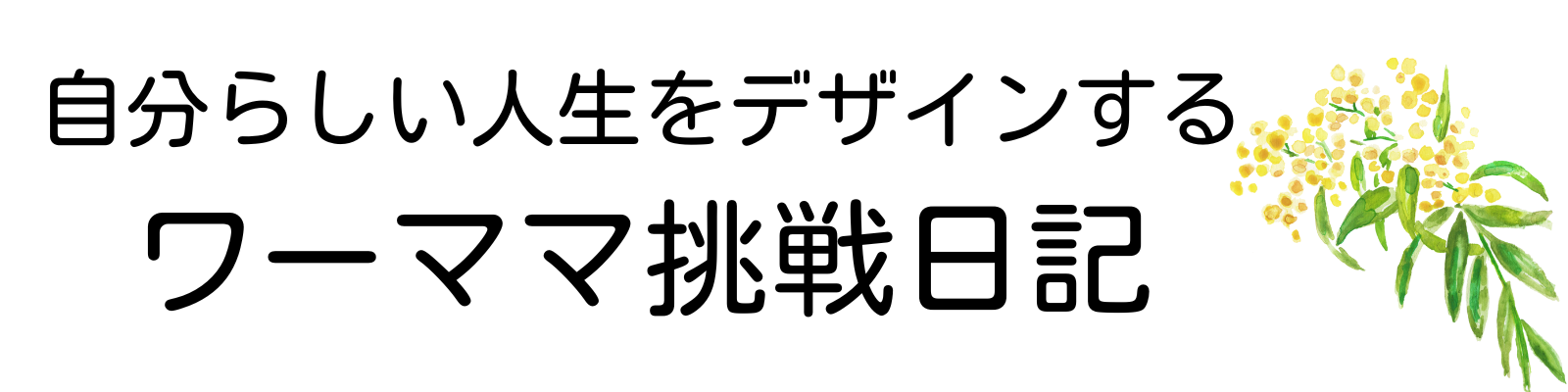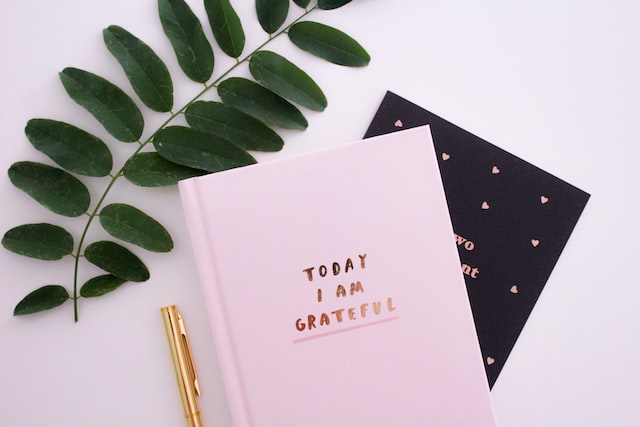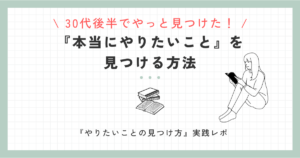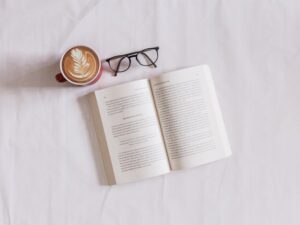もうすぐ出産を控えるママ・プレママさんは「もうすぐ出会う、かわいい我が子とのかけがえない時間を楽しみたい」とその日をたのしみにしていることと思います。
一方で、
「産休・育休中、育児だけで終わらせるのはもったいない気がする!」
「心身共にとにかくたいへんな日々。けど、少しでも自分の時間を充実させたい!」
という思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、第2子出産を控えるわたしが、産休・育休中にじぶんの時間を確保するための工夫を、徹底的に考えてみました。
 kasumi
kasumi第一子の産後は、慣れていないことや肩の力が入り過ぎていたこともあり、復職までほとんど自分の時間は取れませんでした…涙
前提:産後〜育休中は想像以上に過酷!
まず最初に、産後の過酷さについて、私の経験談を踏まえて触れておきます。
私は第1子の産後、予期せぬ様々な体調不良に見舞われて、とにかく体がしんどかったです。寝不足・授乳のトラブルなどの誰もが経験する過酷な日々に加えての体調不良は、正直地獄のようでした。。。またメンタル面でも、産後うつとまではいかないものの、無性に落ち込んだりイライラすることが多かったです。(全部ホルモンバランスのせい、と割り切るようにはしていました)
妊娠前の会社員のワタシが抱いていた産休・育休のイメージはこちら。
「ふわふわの赤ちゃんに癒やされ、ストレスフルな仕事もしなくていいなんて。産休育休って最高」
「育児はたいへんとは聞くものの、実際はママ友ランチをしたりモラトリアムタイムを満喫してるんだろうな…」
そして実際、第一子の妊娠した時の私は、コロナ禍で人には会えないしお出かけも出来ないから、「産休・育休中(こどもの昼寝中や夜寝たあと)、副業を始めて収入を得よう!」と決めていました。
ですが、現実は、夜間授乳でずーっと続く睡眠不足の毎日。朦朧としながらも、赤ちゃんを生かさねばというプレッシャーを感じ気が抜けない日々。
特に初めての育児だったので、日々成長し新しい姿を見せてくれる赤ちゃんに対して、お世話のしかたや、トラブルの対処法を、授乳中などのスキマ時間をつかって、毎日のようにリサーチしていました。
他にも、赤ちゃんのうちから刺激を与えてあげなければという使命感のもと、児童館に毎日のようにお出かけしたり、絵本の読み聞かせをしたりと忙しく育児をしていました。
また、子どもがつかまり立ちを始めると完全に目を離せなくなります。結果、自分の時間が持てたのは、毎日睡眠後2時間の読書タイムを得られた生後3ヶ月頃のみでした。(その後は夜泣きが始まり、睡眠確保が最重要命題でした)
仕事に復帰し保育園に預け始めたときの正直な感想は
「育児という超多忙なプロジェクトから、やっと開放された」
でした。
そんなわけで、復職したとき、私は過去の自分に言いました。
「副業?あー、そういえばそんなこと言ってたね!」
「イヤイヤ、無理でしょ!副業する暇あったら、寝るかわ!」
(※もちろん我が子はとってもかわいくて、しあわせな経験だったのも事実です)
でも、産後〜育休中、じぶん時間を確保することは可能なはず!
そして第2子を妊娠したわたしは、またしても副業にチャレンジしようとしています。あんなに大変だったはずなのに、今、本気でこう思います。
「いやいや、工夫次第で、育休中に副業できるんじゃない?」
それは、実際に育休中に副業を始めた友人(ワンオペ)が周りにいたことや、多くのママがSNSなどで副業を始めているのを、実際にみてきたからです。
ただ、決して簡単なことではないはず。
心身ともに健康で丈夫な方や旦那さんがワンオペ育児してくれる家庭、子どもがよく寝てくれる子やつかまり立ちが遅めの子、などあらゆる条件に恵まれたら別です。
ですが、私のようにほぼワンオペかつ体が弱いタイプは、それ相応の戦略が必要だと思います。(しかも今回は2人育児という未知の領域チャレンジ。)
であれば戦略を立てて実現させてみようと、思っています。
じぶんの時間を確保するための方法
では、具体的にどのようにじぶん時間を確保しようとしているかお伝えします。
具体的な例があった方がイメージが湧きやすいので、私はじぶん時間にやりたい「読書」&「ブログ記事」を想定して書いてみます。
※ただし、先にお伝えしておくと、既にやり遂げたわけでもない私の、あくまでも「計画」です。たぶんムリだろうな…という私の中のもうひとりの現実的な言葉はあえて無視します。
1.実現可能な行動目標を設定をする
まず、1日に取り組めそうな時間をざっくり出して、これをひとつの目標にしてみようと思います。
私の場合、1日最大2時間。
2時間という目標を立てることで、日々の行動を工夫し、時間を捻出するという意識づけのきっかけになればいいなと。
工夫のひとつとして、一時保育やファミサポなどの活用も検討するかもしれません。
(第1子のときはコロナ&子と離れること自体に抵抗があり、活用しなかったです)
——————————————————————————————–
2時間という目標の根拠(試算) ※興味ない方は飛ばしてください
□1人目のときの、ひとり時間=1時間/日(実績)
※育児のリサーチに全部使ってました。。
□今回の、ひとり時間=2時間/日 (試算結果)
計算式:
①日中(上の子は保育園で不在)
・負担感は2人目で慣れているので減るはず
(A) 精神面=前回の1/2=5割
(B) 体力面=前回の2/3×加齢で2割増=7割
→(A+B)/2で、日中の育児の負担は前回の約6割
・保育園(7時間)ー家事や昼ごはん・送迎(2時間)=5時間
5時間のうち、育児に6割の3時間、じぶん時間に4割の2時間を宛てる
②夜
・同時2人育児後のため、ほぼ一緒に寝落ちすることを想定し、0時間
——————————————————————————————–



こどもが昼寝をよくしてくれる子か否かで全然変わりそう



まさに。それに体調最優先というのが大前提!無理はしたくない
2.やらないこと・削ることを決める
第1子の時は、初めてということで色々と力が入っていましたが、今回は肩の力を抜きたいです。
具体的には、下記を想定しています。(思いついたら、書き足します)
・刺激を与える(ex0歳の絵本の読み聞かせ)
→時々話しかける、CDかけ流す、程度で。上の子から十分刺激を得られるはずなので。
・育児、知育のリサーチをしない
→第1子で得た知恵でなんとか乗り切る。育児のリサーチはおわりなき底なし沼…!
・一時保育の活用(あかちゃんからひとときも離れない、をやめる)
→児童館や保育園など安心できる施設での一時保育を積極的に活用する。
・ぴよログ(育児記録)を完璧につけない
→記録するのは、第1子・第2子ともに、睡眠と便と日記のみ。(食事とか散歩とか不要)
・下の子は日中にお世話の一貫としてお風呂に入れてしまう。(夜みんなで、とか考えない。)
→それで、夜の負担感が減ることが、翌朝の作業効率アップにつながる…はず!
一時保育の活用有無が一番大きな分かれ道です。信頼できる団体が既に分かっているので、預けてみようかなと思います。
ただ上の子が保育園から帰って来たら、上の子最優先で愛情を注ぎまくることだけは手を抜きたくないです。
これは色んな人に言われますが、
「きっと上の子は赤ちゃんがえりするはず」
「我慢しがちで寂しい思いも抱えているはずの上の子に、思いきり愛情を注いであげて」
「上の子に注いだ愛情が下の子に流れる」
これはずっと心にとどめておきたいと思います。(もちろん下の子も、思いきり可愛がります!)
3.仕組み化して、取り組む心理的ハードルをさげる
「仕組み化」は、産前にとにかく仕込みたいです。
①作業の定型フォーマット化
まだ勉強中ですが、自分が書きやすくて、かつ納得いく、記事の作成手順や構成を定型化します。記事を毎回1から考えるのは負担感が結構大きいです。今は手探り中ですが、定型化するとこんなメリットがあるのでは?と思ってます。
・1記事あたりにかかる時間が短くなる
・細切れ時間でも、小さなステップごとに進められる(進んでるという達成感を得やすい)
・授乳中や出先などでスマホや紙でも取り組める
そのために、WEBライティングの勉強をして、試行錯誤して自分なりの型をつくります。これは産前になんとしても確立したいです…!
②産後しばらくは、頭を使わずできる作業にあてる
産後に思いきり頭を使う作業をするのは、むずかしいだろうと思っています。(挫折しそう…)今は手探りで方向性を探っている段階です。結構頭を使うので、完全なひとり時間にしか出来ないです(わたしの場合)。
産後は、用意したテーマに沿って、①の定型にのっとって書けばOK、なら、継続できるかなと。産前に、ブログの方向性をある程度定め、これから書くこと・テーマを洗い出しておきたいです。(余裕があれば予約記事投稿も準備しておきたい…!)
まとめ
以上です。
産後には時間的にも体力(そして頭を使うこと)にも制約がかなりあります。ですので、その制約を受け入れ、ハードルを下げる工夫を産前に仕込むめるか、が勝敗を分けそうです。
もちろん、何が起きるかわからないのが出産ですし子育てを舐めてはいけません。育休中のチャレンジは、あくまでノルマなし、個人の無理ない範囲で、少しでもできたらラッキー、くらいの気軽な気持ちでいたほうがいいかなと思います。
そして、体調最優先で。あなたが倒れてしまっては、元も子もありません。
【#1ヶ月書くチャレンジ】
ちなみに、この記事は「#1ヶ月書くチャレンジ」の7日目の記事として書きました。「1ヶ月、与えられたテーマに沿って文章を書き、書く習慣を身に着けよう!」という企画です。本日のテーマは、「最近悩んでいること」。
わたし自身の最近の悩みは、まさに冒頭の書いてあるように「ブログの執筆を、産後も続けられる自信がない」ことだったので、自分の産後のためにも今回の記事を書いてみました。
こちらの本にテーマが載っています↓