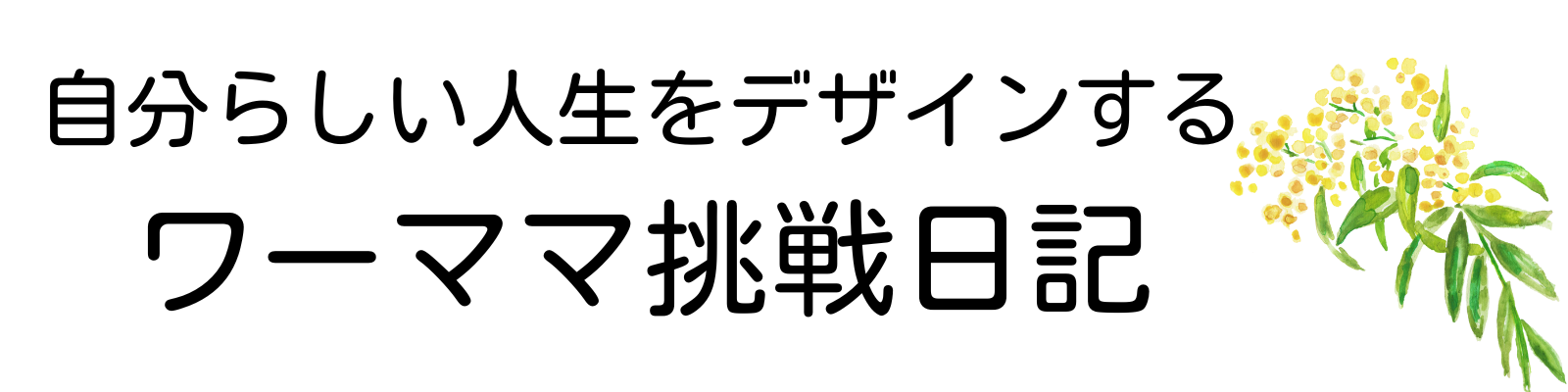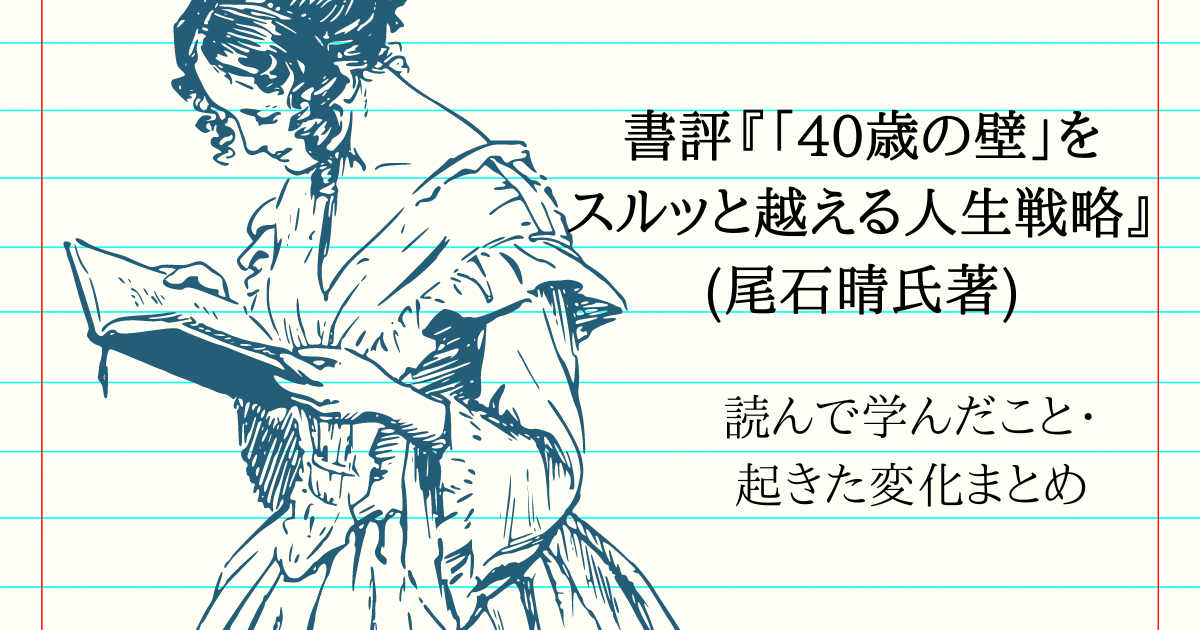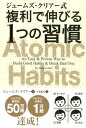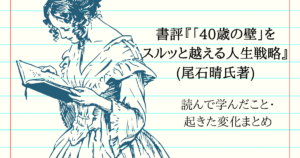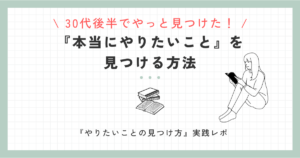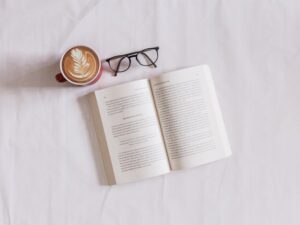2月は10冊の書籍を読みました。その中でも、特に学びの多かった本をご紹介します。
『「40歳の壁」をスルッと越える人生戦略 』(尾石晴氏著)
・「子育てまっただ中でも、自分のキャリアをもっと前向きに考えたい」
・「今の働き方を変えたくても、どうしていいかわからない」
・「周囲にロールモデルがいない。誰かの生き方を参考にしたい」
 kasumi
kasumi最近voicyもよく聞いている、私的には超注目の著者さんの最新刊です!(2023.2時点)
本の概要
『「40歳の壁」をスルッと越える人生戦略 』は、現代の40歳前後の女性に向けた、これからの生き方を考えるための本です。最近よく聞く「複業」という働き方を推奨されており、ご自身の体験をもとに、キャリアに関する考え方から、複業を作り出す具体的な方法論まで、分かりやすく解説してくれています。
尾石晴さんは、40歳手前で新卒より16年勤めた外資系企業を卒業され、サバティカルタイム(使途用途を決めない学びの休暇)を過ごし、オンライン・スタジオヨガ「ポスパム」、母と子のスキンケアブランド「soin(ソワン)」を立ち上げられました。2022年春から大学院に進学。同時に、文筆家やvoicyのトップパーソナリティ、不動産経営など幅広く活躍されています。



現代社会のワーママの、新しいロールモデルですね。



経歴がすごすぎる…
読んだ感想
今モヤモヤを抱えていること自体を肯定的に捉えられるようになった
40歳手前で第二子妊娠中に今後のキャリアを考え始めた私にとって、著者の下記のメッセージは心に響くものがありました。
40歳前後で人生の後半戦について真剣に考え、自分のモヤモヤに向き合っていくことは、決して無駄にはならない。
『「40歳の壁」をスルッと越える人生戦略 』より引用・加工
ママ向けの育児支援制度が比較的充実した会社で働いているため、周囲の同僚たちの考えは「小さな子どもがいるし、キャリアはひとまず現状維持」一択です。特にある程度やりがいも感じられる年次なので、「大変ながらも今の仕事は好き」という同世代の同僚も割と多いです。
そんな中、今の仕事・お金・安定した地位より、もっと自分が大事なこと(自分のやりがい)に重きを置きたい、と考えているのはごくごく少数派。
会社員を辞めて活躍されている著者の存在と、具体的なプロセスを読んで、「実際にこんな生き方をしている人がいる!」という勇気をもらえたのが大きな成果でした。
また、もうひとつ心が軽くなったポイントがあります。それは、「会社辞める決断ができない」のは、現状維持バイアスという思考が働くためだということ。決して私が保守的過ぎるとか優柔不断とか行動力がない、ということではないんだな、ということが分かり、過去の自分を肯定的に捉え直すきっかけとなりました。
複業育成のために、これから考えるべきこと・すべきことが具体的になった
複業=複数の本業に取り組む働き方、を指します。「副業」との違いがポイントで、副業の場合は、本業がメインで、副業はあくまでサブ、という位置づけになります。
この複業をどうやって作っていくか、には大事なポイントがあります。それは、本業で感じるデメリットをせっかく始める複業でも引きずってしまいがちだという点です。例えば、ストレスの原因となるような人間関係が付随してしまう複業の設計だったり、主目的が「お金のため」になってしまうこと、などです。
せっかく始める複業では、余計なストレスを回避するために、自分の価値観や得意なこと・好きなことからビジネスモデルを構築していくことが大事です。そのビジネスモデルの構築方法のとっかかりの考え方が書かれている点が、非常に参考になりました!
ネタバレは避けたいのですが、ひとつだけ参考になった部分をピックアップします。
例)複業で得たい報酬は何かを考え直す
必ずしもすべての複業で、金銭的報酬を得る必要はないというのが著者の主張です。そして、報酬には他に、精神的・信頼的・貢献的な報酬というものがあるそうです。
これを見て、「会社で金銭的報酬、それ以外の複業で精神的・信頼的・貢献的報酬に重きを置く」というすみ分けもありだと感じました。
会社員として働くこと自体、正直あまり向いてないような気もしつつも、結構好きな部分もあります。あえて会社員としての地位を全部捨ててしまうのではなく、会社とそれ以外の複業で役割分担をしてしまえば、会社に求めすぎない、という選択肢も出てくるのだな、と感じました。
他にも、金銭的報酬=会社+投資の両方に分担させる仕組みを作ることで、若干ストレスが多めの会社は時短勤務にする、という選択肢も現実的だなと感じました。
また、複業は最初からマネタイズを狙うのではなく、精神的報酬などを得ながら最終的にどの複業か、ひとつでもマネタイズできればラッキーと考えると始めやすくなると感じました。
読後のTODO&はじめたこと
最後に、私が本書を読んだあと、どんな行動を心がけているか、また心がけていこうとしているか、をご紹介します。
思考を言語化する努力
本書でも推奨している「やりたいこと100リスト作り」。私も年初から時々やっているのですが、今年のリストづくりでは、あまり思い浮かばないことにがっくり来ていたところです。
ですが、このリスト作りも何年も続けるうちに精度が上がってくる&貧相でもその中にはキラリと未来につながる原石が含まれているかもしれない、と書かれていました。リストがどうもしっくりこない場合、思考や潜在意識がまだ十分に言語化できていない、ということなんだと思います。
言語化の精度を高めるには、ひたすら言語でアウトプットし続けブラッシュアップしていくしかない。インプットしながらアウトプットを継続することを改めて肝に銘じました。
毎日小さくても前向きに行動し続ける
「今はモヤモヤの真っ只中にいるとしても、日々の小さな変化を積み重ねていくことで数年後には思いもしない場所にたどり着いているかもしれない。」
本書を読んだのは2週間程前ですが、このような思考で毎日を過ごす習慣がついてきた結果、子どもとずっと一緒に過ごす週末でも読書量が以前より増えました。
また、AmazonAudible・voicyなど新しいインプット方法を取り入れてみたり、日々のルーチンの効率化にも着手するようになりました。(他にもインプット→アウトプットのための音声入力や、スマホ・PC連動のグーグルドキュメントの活用。)
著者のあとがきを読んで、こんな偉業を成し遂げている人でも、いきなり大きな進化を遂げたのではないということが分かります。著者ご自身も、「変化とは小さな行動から始まります。」とおっしゃっているので励みになります。
ちなみに今Audibleで読んでいる『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』で、更に習慣の重要性をより深く理解できました。これを読むことで、習慣化のモチベーションがだいぶあがったのでオススメです。
優秀な人の思考に触れる時間を増やし、自分をアップデート
尾石晴さんの本を読んだのもブログを読んだのもごくごく最近ですが、彼女をロールモデルのひとりにしたいと思いました。色々すごい方ですが私が特に尊敬する点は「思考力」です。
自分が感じる違和感を言語化するスキルや、問題を分解してひとつひとつ解決策を立てて行動するところも尊敬します。
私も自分の思考力・言語化能力をもっと高めていきたいので、インプット元として尾石晴さんのvoicyやnoteも購買し刺激を受けることにしました!
他のロールモデルの思考にもオンラインや書籍でなるべく触れるよう心がけています。(勝間和代さんなど)



voicyは有料回(プレミアムリスナー)の方がやはり有益なので、聞きたいテーマがあれば、お金は惜しまないことにしています◎
まとめ
本書を読んで、「育休中に複業を育てよう!」という決意がより強まりました。また、日々の生活に変化が起きたのは間違いなくて、本当に読んでよかったです!これは、尾石晴さんの知的で優しい人柄が好きなことに加え、同世代・同性なので価値観や思考がすんなり受け入れやすいからだと思います。



著者の他の本も読んでみたい!