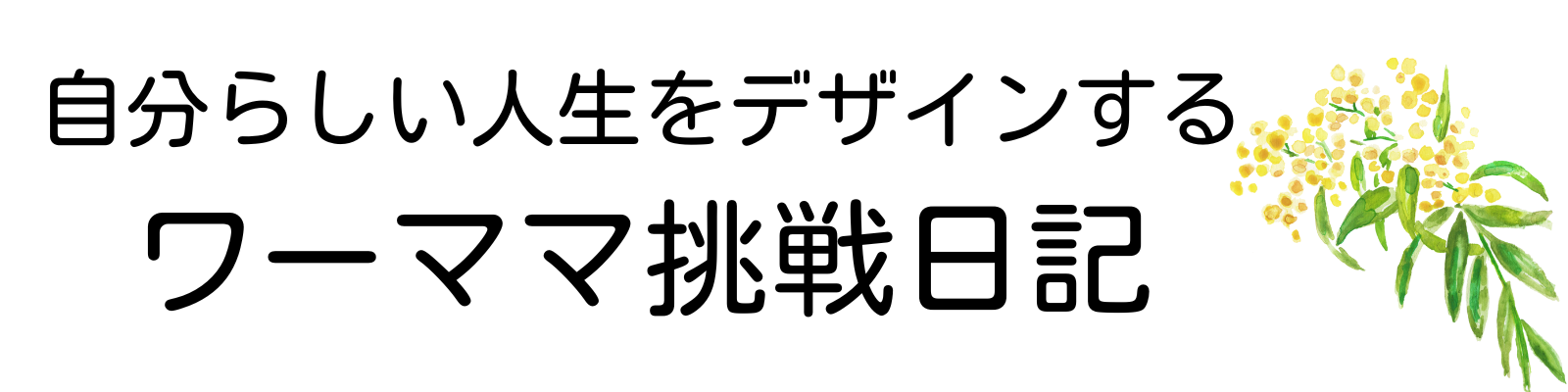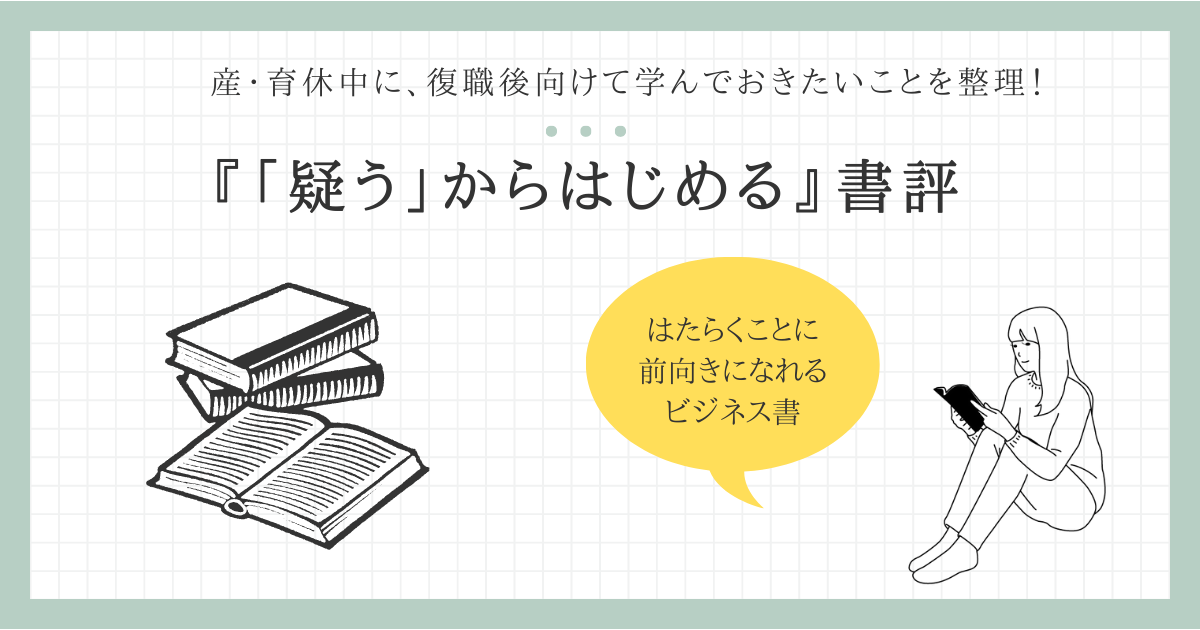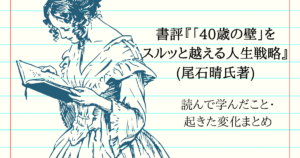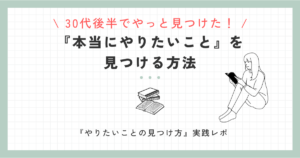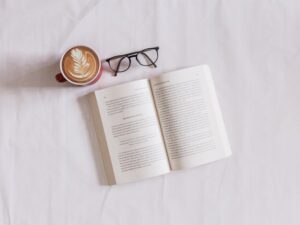2月に10冊の本を読みましたがその中でも特に参考になった本をピックアップします。
この本はこんな人にオススメ!
・会社での同調圧力にモヤモヤしている会社員
・やりがいを感じながら働く方法を知りたい人
・日系企業で働いている全社員(に読んで欲しい)
本の概要
『「疑う」からはじめる。〜これからの時代を生き抜く思考・行動の源泉〜』
本書は、日本企業にあたりまえに存在する悪しき慣習をピックアップし、<何がおかしいのか><本来どうあるべきか>という気づきを与えてくれます。
また、そのような悪しき慣習がはびこる環境下で前向きに自分のキャリアを形成するには、どんなマインドでどんなことに取り組めばよいのか、について書かれています。
著者の澤円氏は、会社員として偉業を成し遂げた実績のある方。その実績とは、マイクロソフトで年間200本ものプレゼンテーションを行い、ビル・ゲイツからも絶賛され、Microsoft名物エバンジェリストとして『プレゼンテーションの神様』とも言われた(wikipediaより抜粋)というもの。現在はマイクロソフトを退社され、複業で多方面で活躍されていらっしゃいます。
読んだ感想
自分の職場をグローバル視点で客観視でき、色々腹落ちした
新卒で入社し15年近く一つの会社で働いてきたため、自社の比較対象がなく、「会社ってこんなものか」と思いこんでいる方は多いと思います。私もまさにその一人。そのため、ひとりモヤモヤを抱え続けて働いていた時期や、ランチのたびに同僚と愚痴りあって発散していた時期などが長くありながらも、そんなものだから自分が適応するしかない、と思っていました。
ですが、この本を読んで、「グローバル企業のマネジメントってこうなのか!」「海外の会社だとこういう時にこういう対応になるのか!」という驚きの具体的事例が沢山紹介されていて、正直目から鱗の連続でした。
これを読んで私の会社でありがちな例を思いついたので1つ挙げます。
長時間労働が発生したときの上司の対応、日本企業とグローバル企業のちがい
①「残業続きの日々、お疲れ様!飲み会でもして慰労しよう!」 (→飲み会も疲れるんですが)
②「繁忙期だから仕方ない。無事乗り切れてお疲れ様でした!」 (→繁忙期ばっかりなんですが)
③「残業が多いようだけど、このご時世残業は控えて。」(→サービス残業しろと?)
→結果、長時間労働を改善しようとする人は誰もおらず、状況は変わらない。
正直、私はこれが当たり前の会社でずっと働いていました。残業も割とこなして来たのですが、「頑張ったね、おつかれさま!」と言ってもらいながらも、特にそれで給料が劇的に増えるわけでもないというのがデフォルト。会社員だから、そんなものだと思っていました。
「こんなに残業が増えるなんて、効率化できるプロセスがあるかも。見直して無駄を省こう。」
「もしかして苦手な仕事なのかな。配置転換を検討してみよう。」
→長時間労働を問題として認識。仮説を出して検証し、改善につなげる。
(海外では対応しないと、優秀な人はどんどん離れていってしまうという背景の違いもある。)
こういった対応が検討されると知って衝撃を受けました…!
でも、これがあるべき姿だなと心から感じます。日本ではマネジメントがあまり行われていないこと、グローバル視点でのマネジメントとは、このように決断を下し続けること、ということも知りました。
育休明けの復職後、どんなマインドで働くかの指針が出来た
実は、産休に入る前、過去にない程に今の仕事のモチベーションが下がってしまっていました(涙)。また職場の慣習にも不信感を抱いたままお休みに入ったため、後味の悪い感情を引きずっていました。
本書を読むにあたって、「この感情にどう対処するか。復職後どういうマインドで働けばいいのか」について、ヒントを得たいと思って読んだのですが、、、
この本を読んで、自分なりに、復職後のスタンスの立て直しの目処を立てることができました。そのために、すべきこととして以下を考えています。
慣例を常識で済まさず「それおかしくない?」と認識する心がけ(今も復職後も)
「会社にある”違和感”にどう対処すべきか」言語化できるよう勉強する(育休中)
主体的にやりがいを持って働くための準備をする(育休中)
どんな環境でも主体的に成果を出すべく、学びを実践・検証する(復職後)
 kasumi
kasumiこの本を通して「未来志向」でありたい、と思えるようになったのも大きな成果。(読んで前向きな気分になれました!)
読後のTODO
先ほど挙げた4つのすべきことのうち、2と3についてもう少し詳しく書いていきます。(見出しのナンバリングは2→1、3→2にしています)
1. 「会社にある”違和感”にどう対処すべきか」言語化できるよう勉強する(育休中)
これからずっと会社員で居続けるのか、辞めてしまうのかは、現時点では分かりません。ただ、15年も会社員として働き続けてきた以上、これまでのキャリアをしっかり棚卸ししたいと考えています。
具体的には、
- 自分の強みをより磨き上げるため、言語化する ※先日の自己分析でもまだ出し切れていない感
- 何がストレス要因で、次の道(キャリア)で避けるべきストレス要因が何かを明確にする
必ずしも器用にうまく立ち回れるタイプではなく、ついぐっと堪えて流してしまいがちな私としては、「あの時どうすべきだったか」「本来どうあるべきか」「次はどういう環境で働きたいか」を考える際に、もう少し広い世界(グローバルスタンダード)を知っておく必要があると思います。
マネジメント・組織論・キャリア・ストレングスファインダー・人間関係・心理学…
いわゆるビジネス書は「問題に向き合うためストレス要因になる」と思って長く避けてきた私ですが、今は「問題に向き合うために読みたい」本が山程あります。
これを可能な限り、育休中に読みます。
(偶然なのか、前に記事に書いた『本当にやりたいこと』に繋がりそうな本ばかりです…)
2. 主体的にやりがいを持って働くための準備をする(育休中)
最近読む自己啓発系の本でほぼ全てに書いているのが、「得意なことを明確にしてそれを磨く」ことの重要性です。
本書では、その重要性を大きく2つの視点から述べていました。
限られた勤務時間でタスクを終わらせるコツは、得意なことに特化して取り組むこと。
その代わり苦手なことはそれが得意な人に任せる。win-winになるよう自分の得意で先に貸しを作ろう。
会社以外の「外のものさし」で客観的に自分の強みを図り、会社に頼らない自分の肩書きを作ろう。
それが、会社で主体的に働く際の大きな原動力や精神的余裕につながり、複業にもつながる。
会社で働く際に欠かせないのが1の時間管理です。2に関しては会社でどんな困難にぶち当たっても、「自分主体」で成果を出し続けるぞ、というスタンスを維持するためには欠かせないものとして紹介されていました。
この得意なことを言語化し磨き上げることが、会社での働きやすさ=ストレス対処スキルの向上にもつながる、というのは個人的に新たな発見でした。
ちなみに、この本には、得意なことが見つからない人に向けた見つけ方の例が書かれていて、おかげで私は自分の得意なことが更に3つくらい思い浮かびました。(うれしい〜)
また、その得意なことが社外でどの程度評価されているのかを知るため、活動を広げよう・アウトプットをしようという提案もありました。それが結果的に得意なことを更に磨くことにもつながるというのも納得です。
こうしてブログを書いたりTwitterをして言語化して人の目に晒すことには意味があるなと再認識しました。
まとめ(本書で学んだ一番大事なこと!)
これまで書いてきた内容は、本書を読んで自分がどういうことに取り組みたいかです。
では、本書で学んだ、いちばん大切なことを最後に書きます。
- 世の中はよい方向に変わると信じて「未来志向」で働き続けること
- みんなのハッピーな姿を思い描き、言語化し、ともに未来へ進もうと働きかけること
こういう姿勢を持ち続けることの大切さって、今の時代あまり誰も語りません。私も完全に目の前の仕事をこなすのに必死で、意識からモレてました。
むしろ、そんなこと学生の夢の話で、実際働いているうちに「ちゃんと仕事回して貢献していること>未来志向とか夢を語ること」という方程式が頭の中で固定化されてしまっていました。
(会社で夢を語る人=仕事はまったく出来ないというケースがあまりに多いからだと思います。両立出来ている人っているのでしょうか。あ、それが出来ているのが、澤円さんですね。他にも沢山いらっしゃるはず。。。)
少し会社と離れている今こそ、こういう仕事の原点を思い出しつつ、それを実現するためのスキルアップ・知識強化もセットで身につけたいな、と思いました。



元気が出る本でした。図書館で借りましたが、購入して本棚に入れておきました。時々読みたいです。